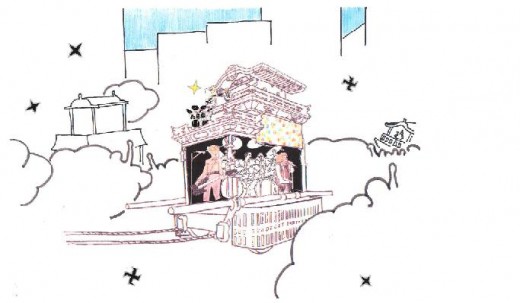二人組みのアートユニット「KOSUGE1-16」として活動されているアーティストの土谷享さん。「作品を通して人と人との関係性をつくる」というコンセプトのもと、これまで多くのアートプロジェクトを手がけてこられました。昨年12月のシブヤ大学での公開ラボでは、「長者町山車プロジェクト」の事例を中心に、アートを介した関係づくりの実践を紹介して頂きましたが、中でも印象的だったのが、「面倒をかけることで一過性ではない関係性が生まれてくる」という考え方でした。
この一見、逆説的な考え方を土谷さん持つに至った背景や実際の関係づくりの現場で起きていることについて、土谷さんにお話を伺いました。
(取材:2012年2月14日、聞き手:ソーシャルセンシングラボ主宰・井上岳一)
※シブヤ大学での講演の様子はこちらをご覧ください。
- KOSUGE1-16は、「生活を共にすることで生まれる共有フォルダ」という考えから始まったんです
井上: 以前、企画を固める前に現場でのリサーチを徹底的にされると仰っておられましたが、企画案というのは現場で練り上げていくものなのでしょうか?
土谷: 企画の大枠というのは、現場に行く前にだいたい決まってますね。ある程度ひらめきなんですけど。事前のやり取りでだいたい状況は分かるので、「やりたいことのストック」の中から「これかな?」と思うものをひっぱりだすというか。
長者町山車プロジェクトの場合だと、もともと話が来る前から山車の造形に興味があって、いつかはつくりたいなと思ってました。そんなときに長者町の話が来て、愛知トリエンナーレのキュレーターから山車が戦争で焼けて無くなったという話を聞きました。名古屋の風習などを調べてみると、昔から山車の文化があるんですね。これならみんなもついて来てくれるんじゃないかなと思って、当初描いた絵がこれです。古いものと新しいものの融合というイメージで描きました。
井上: KOSUGE1-16は実生活では夫婦関係にあるお二人のユニットですが、こういうアイデアとか絵を考える時、お二人のどちらがされるのでしょうか?
土谷: この絵はたまたま私が描きましたが、妻が描くときもあります。もともと、KOSUGE1-16は、「生活を共にすることで生まれる共有フォルダ」という考えから始まったんです。
2001年頃、妻と一緒に手伝っていたプロジェクトがあって、その関係で企画展に出展してみないかという話があったのですが、そのとき思いついたアイデアを話すと、妻も全く同じことを考えていたんです。で、互いに「これは僕が思いついたんだ!」とかなっちゃったんですが、話を聞くと、以前一緒に東京タワーに上ったときに見ていた風景からふたりとも着想を得ていたことが分かったんです。それならいっそ屋号をつけてユニットで出そうかと。それがKOSUGE1-16のはじまりなんです。
そもそも妻とはアートに対する違和感とか危機感を共有していて、その前提で生活していく中で「あの時こう思ったんだけど」という話をすると「そうだね」となるというか。やりたいことのストックを妻と共有しているんだと思います。
井上: ユニットとしての活動するようになって、一人で活動されていた時とどんな点に違いがあるのでしょうか?
土谷: 自分だけで考えない、ということですかね。一人で考えていると、どんどん自分を掘り下げて煮詰まっちゃうのですが、それが無い。一人でアーティスト活動をやっている人は、すごく強靭というか、自分を客観視できる人だと思うんですが、二人ともそういうところは弱いんだと思います。だけど、そういう強靭な人しか作家として成立しないという時代じゃないと思うし、2人でも10人でも、ユニットとして活動できる時代だと思います。
井上: 見つめる自分と掘り下げる自分があったとして、一人でやっていると、掘り下げる部分が強くなってしまう、ということでしょうか。
土谷: そうです。で、やっていくうちに「なんてつまんないことをやっているんだろう」とか思っちゃう。演算数というか、一人だと、処理能力が遅いんだと思います。人に言ったほうが早く進む。
井上: なるほど、土谷さんが掘り下げている時には奥さんが客観的に見ていて、奥さんが掘り下げている時には土谷さんが客観的に見ている。そうすることで、演算も増える、ということでしょうか。
土谷: そうですね。ネットで脳内診断とかすると、僕は圧倒的に女性脳なんですよ。妻も女性脳なんですが、僕のほうが顕著に出ていて。きっと、右脳と左脳をつないでいる部分、脳梁が太いんだと思います。
井上: 脳梁が太い、というのは、具体的にはどういうイメージですか?
土谷: 割と直観的に色々と気づくんです。男性脳の人はロジカルにモノを考えるのだと思うんですが、「だってこう思うんだもん」とか割といっちゃう。
井上: 面白いですね。右脳と左脳では、左脳のほうが大きいのですが、実は先にあったのは右脳で、左脳の右脳よりも大きな部分というのは、後からくっついたものだそうですよ。
土谷: コンピューターを持ったんですね。
井上: そうです。で、そのコンピューターを機能させるには、ベースにある右脳をきちんと動かさなくてはいけない。今、ビジネスの世界でも、デザインを取り入れたりとか、右脳を活用しようという動きがありますが、これも、左脳だけで考えていてはダメなんじゃないか、右脳をきちんと使わないとダメなんじゃないか、ということの現れではないかと見ています。
土谷: もしかしたら、私と妻は右脳を共有しているのかもしれないですね。バーチャル右脳というか…。
自分だけで考えられないので、甘えているだけかもしれないですけどね。一人で考え進めて、自分の中から出てくることに魅力を感じないタイプなんで。人と話すことで強度が増すというか。だから、彼女をそういうふうに使っているのかもしれないですね。
実は、アーティストとしての活動は、KOSUGE1-16以外にもやっていて、最近でいうと、「BUGHAUS(バグハウス)」という活動を2010年の 年末からスタートしています。これは土谷享が個人で参加している活動ですね。「ポスト工務店」というコンセプトで、工務店の下職として30歳代〜50歳代のアーティストや異業種のクリエイターを抱えていて、私もその下職の1人です。既にいくつかの案件を抱えていますが、建物を造る事から住まいに関するワークショップまで幅広く展開できると考えています。
子どもの頃から年上の人と遊んでるほうが楽しいんですよ。同じ考えの人たちで固まるのは嫌だなぁと思っていて、少年野球の子どもたちがいつも一緒に帰ったりしてるのを見て「気持ち悪いなぁ」とか思ってました(笑)。
- 関わったプロジェクトには自立していってほしい
井上: 以前、日の出町のゴミ処理場建設に反対するアーティスト達のトラスト運動に関わった経験が大きかった、というお話を伺いましたが、それはアーティストとしての考え方や姿勢にどんな影響があったのでしょうか?
土谷: トラスト運動に関わったのは、私が高校を出て美大受験の準備をしている時でした。専門的な技術も学べる高校に行っていたせいで、高校卒業時点ではデッサンなども結構できるようになっていて、予備校の特待生になっちゃったんですね。代わりに、東京芸大しか受験しちゃだめ、という縛りがあって。延々と受験に通るために絵を描いていたのですが、当時、「絵を描くのってこんなにつまんないことなのか」とずっと思っていました。
そんな時にトラスト運動と出会って、衝撃を受けましたね。表現することが生き方になってる人たちに巡り合えたわけです。しかもなんかしらないけど東京都と戦ってる、みたいな。おまけに、海外の巨匠も土地を買ったりしていて。
全然知らないことだらけだったので、脳も活性化されて、友達も連れて行ったりして、いきなり興味がそっちにいっちゃって。そのうちに、予備校の先生は、東京芸大出てるかもしれないけど、作家でも無いしなんなんだろうなとか思い始めて。それで、特待生の契約を無視して、私大とかも受けて、とにかくこの場所から抜け出そうとしてました。
大学に行ってからも、授業にはあまり興味が持てなくて、トラスト運動に行くか、中村政人さんのコマンドNのお手伝いをしたりしてました。
井上: 同じような人たちが同じところに集まって同じことをしている、というのが耐えられないんですね。
土谷: そう、耐えられない。その頃、コマンドNでは「秋葉原TV」というプロジェクトをやっていて、秋葉原の電気屋さんのTVモニターやコンピューターにアーティストのつくった映像を流すっていうプロジェクトなんですけど、アートなんか全然興味ない電気店の主任さんなんかを説得しに行っているほうが、授業を受けているよりもずっと刺激的でした。
井上: 以前、アート業界の中で競技者のように生きる「アスリートアート」にはなりたくないと仰っていましたが、アートという業界よりも実社会のほうに興味がある、ということでしょうか?
土谷: 知らないことに出会う、「小さな冒険」が好きなんだと思います。それが無いとモチベーションがあがらない。お互い知らない人同士のほうが、色んなアイデアが出てくる。
井上: 土谷さんは、アートじゃないところにあえてアートを持ち込む人ですよね。
土谷: いうなればそうかも知れないですね。ただ、商店街なんかを使って、既存の施設じゃないところでアートフェスティバルをやるとか、そういう括りの中にKOSUGE1-16は見られがちなんですけど、実はそういうことはほとんどしたことなくて、「アートを街に開こう」とか言って、シャッター商店街をアートで埋め尽くすことのほうに違和感があるんです。大航海時代じゃないけど、知らないところに上から目線で何かを届けに行く、という文脈は苦手なんですよ。それって魚屋さんと同じ目線じゃないですよね。助成金もらってアートイベントやって、それが終わったらいなくなっちゃうわけだし。
井上: アートを社会に開いていく、と言いながら、実はアートが社会から屹立しちゃってる。
土谷: そうですね。逆ですよね、「どや!」みたいな。よそ様との違いを強調したいだけのように見えるんですよ。
井上: アートを社会に開く、というときに、そういう大航海時代みたいなやり方が一つあるとしたら、土谷さんの冒険はどんな冒険なんでしょうか?
土谷: すごく個人的な冒険なのかな、と思います。戦法としてはゲリラ戦なのかな。だから、自分がアーティストとしてリスペクトされるかどうか、とか、表現したことがアートとして括られるかどうかということには興味はないんですよ。ただ、自分が関わったアート活動には自立していってほしい。その思いはかなり人よりも強いと思います。
- アートは、世の中に不足しているビタミン、みたいなもの
井上: 「自立していってほしい」という思いはどうして生まれてきたんでしょうか?
土谷: トラスト運動やコマンドNの活動をしていたときに体感した「強さ」、そこで僕が個人的に感じた強さみたいな部分があるのかもしれないですね。それは学者さんとかお医者さんとか、ある種の専門家の人たちはやろうとしないことに、横断的にズカズカと入っていけるというのがアートの面白さなのかなと思うんですね。「誰もやったこと無いけど、進めていこう!」というエネルギーに満ちていると思うんですよ。で、それはアーティストが独占しているものではなくて、例えば大工さんでもできること。アーティストって始めからそこのリミットが切れてる、図々しい存在だと思うんですね。
井上: 境界が無い、ということですか?
土谷: 技法とか、手法とか、手段を選ばないというか、例えば、そこにしゃもじがあったら、それでも戦える。例えば料理人さんだったら、自分の包丁が無いと無理だと思うかもしれないし、絵描きさんだったら、絵の具が無いと無理と思うかもしれない。アートの場合は、何にも無くてもピンで攻略していけるというか、進んでいけるというか、そういうずるい位置にあって、そのずるさを存分に使ってみたいんですよね。
井上: もともとアート自体に越境性みたいなものがある、ということでしょうか?
土谷: 越境性…。革命みたいな感じですかね。
井上: 革命ですか…。壁をどんどん壊していく、というようなイメージですか?
土谷: 壁というか…。例えば、同じ地続きなものでも、見方とか変われば全然違う風に変わるじゃないですか。そういう感じなんですけどね。
井上: なるほど。あえて壊さなくても、見方を変えるだけで全然違うものに見えてくる。
土谷: そうそう。そういうものがいっぱい世の中にあるほうが、色んなことが早いと思うんですよね。それは、言葉にすると例えば本当の意味でのリスペクトだったり、スポーツで言ったらスポーツマンシップだったりするのかもしれないですが。それってシステムじゃなくて個人個人の問題だと思うんですね。だから、アートが社会に役立つというときに、上位レベルでシステムを提案して行っても、結局また同じだと思っていて、個人と個人のゲリラ戦のほうが実は戦い甲斐があるんじゃないかなと。
井上: そこで土谷さんが戦う相手とは何なんでしょうか?先ほど「早い」と仰いましたが、その言葉からは、ある種の到達したい理想とした世界があって、それに対して社会か個人が変わっていく、というイメージがあるのかな、という印象を受けたのですが。
土谷: 生活の技術、みたいなものだと思うんですよ、その革命は。
例えば、先日、井上さんが、今のサラリーマンの人たちの多くが家と会社で二重の人格を持っている、という話をされていましたが、そうならなくて良くなると思うんですよね、その技術を持っていたら。
世の中に不足しているビタミン、みたいにアートを捉えていて、それを摂取する機会を増やすというか、こうしたらもっとビタミンが取れるんじゃないですかとか、新しいビタミンがありますよとか・・・。そういうエクスチェンジ(=交換)の回数を急激に増やすのが僕にとってのアートプロジェクトなのかもしれないですね。
なので、KOSUGE1-16のユニットが成立している状況って、たぶん100年後は意味が無かったりすると思うんです。テンポラリーなプロジェクトなのかもしれない。もう10年ちょっとやっていますが、うすうす古臭さも感じているので。具体的には良く分からないんだけど、次の時代のことをやらなくちゃな、と思い始めている自分もいます。
井上: それは、予感のようなものですか?それとも、ある象徴的な出来事があってそう感じるようになったのでしょうか?
土谷: なんでしょう、全体的に、ですね。
井上: 最近、東北の被災地に通っているのですが、20代の子たちがすごくいいんです。もともと町の人間じゃなくって、東京から来てたりするんですが、町単位じゃなくて村に根付いて活動していて、すごく村からも受け入れられてるんですね。素晴らしいなと思うのは、彼らは、震災の前と後で変わっていなくて、たまたま震災があったから東北に来て活動をしているという感じで、すごく自然体なんです。気負いが無い。おまけに英語への苦手意識も無い。そういう子たちがフェイスブックでみんなつながっていて、まさにデジタルネイティブって感じで、オープンで、自己一致していて、そして、対話が上手なんです。先ほど出てきた「生活の技術」がすごく高い気がしています。
土谷: アーティストの世界でも、20代は軽やかですね、飄々としていて。他の人を巻き込むこともできるし、それで仲がいいんです。
井上: そういうオープンな人がマジョリティになってくると、KOSUGE1-16という存在はいらなくなるのかもしれないですね。
土谷: そうですね。KOSUGE1-16のコンセプトにある、世の中に欲しかったものが芽生えてきている気がします。そうなると次だなと。ただ、これって日本特有のことなんでしょうかね?
井上: そこなんですが、私はデジタルネイティブなんだと思うんです。インターネット的価値感を持った人間が、国を超えてつながっていくんではないかと。
土谷: 私が学生の頃、シンガポールとか韓国とかで、アート活動を積極的にしていたことがあるのですが、その頃に出会った華僑の人たちが国とか関係なく軽やかに動いているのを見て、きっと一生かなわないんだろうなと思ったんです。でも、同じような空気感を持った子たちが日本でも出てきているんだなと思いますね。
KOSUGE1-16の次の展開としては、場所を変えることなのかなと思っています。
イギリスのバーミンガムで展覧会をする話が進んでいるんですが、そこのキュレーターが「持ちつ持たれつ」というのに注目してくれていて。バーミンガムは、アートミュージアムには白人しか来ないのですが、周りは中東の人とかがいっぱい住んでいて、人種間の断絶がすごくある。それと世代間の断絶も。それを「持ちつ持たれつ」でなんとかできないか、と言われていて。
井上: 「持ちつ持たれつ」って表現は、英語にはないですよね。
土谷: なのでローマ字で表記してるんです。「win-win」でもないですし、「give and take」でもない。
井上: 「give and given」が近いかも知れないですね。
土谷: 彼らは、日本語を理解しているわけではないのですが、「持ちつ持たれつ」の概念は僕らよりよく理解しているぐらいなんですね。今後もKOSUGE1-16をやっていくのなら、システム化やチーム化といった得意技が活かせるところでやる、場所を変えるというのが次の大きなアクションだろうなと思っています。
- 持続力をつけて、自立させる
井上: 先ほど、「自分が関わったアートプロジェクトには自立していって欲しい」という話がありましたが、プロジェクトを自立させるというのは、どういうことなんでしょうか?
土谷: アート作品であれば、お金と交換する、つまり、売れれば商品として自立するわけですが、KOSUGE1-16の場合は手を離れるときの「交換」が無いので、「ぜひ今後とも関わってください」となってしまいます。そういう意味では、KOSUGE1-16なりに手放す方法を模索してきたとも言えます。というのも、「アート」というのはやはり手を離れるものだと思うし、それがアート、表現の社会化の一端を担う要素だと思うんです。
といっても、手を離すのは実はとても面倒なんです。でも手放して進まなきゃという思いもあって。その中でも最も面倒なことが「持続させる」ってことですよね。「持続力をつけて手を離す」。
井上: 持続力に対するこだわりというのは、どこから来ているのでしょうか?
土谷: アートプロジェクトを手放すときの方法として、商品化してしまうというやり方もあります。記録をとって、物語に仕立て上げて、アーティストのサインをして、出版する、というような自分の物語にしてしまうというやり方なんですが、それに対しては「嘘だろ~」という思いがあって。とてもデモンストレーション的というか、そこにクリンチしていても仕方がない。本物になっていくには、その先ですよね。もともと誰がやったのか分からなくなったとしても、習慣化しているとか。そういう無形文化財的な部分。そういう、持続力をつけて手を離すところを目指したほうが、強度が上がると思うんです。
井上: 持続力をつけるためには、どうしたらいいんでしょうか?
土谷: 任せること、ですね。「そういうことがしたいなら、こうしたらいいんじゃない?」と勝手に思ってくれるようにもって行く。そうすると、興味を持ってくれる人、手伝ってくれる人が次第に増えてくる。
長者町の山車プロジェクトのときも、山車のデザインは名古屋のやる気のある若手の人たち(ミラクルファクトリー)に任せちゃったんです。デザイン的に気になるところがあっても、口出しはしないようにしましたね。どうしてそうしたのかは一応聞きますが。
ただ、企画のコンセプト、基幹に関わる部分で「絶対違う」と思ったら、ケンカしてでも口出しします。例えば、「どんどこ!巨大紙相撲」のときにも、懸賞の分配の仕方でケンカをしたんです。主催者の一人が、「懸賞は勝ち負けに関係なく平等に分配しよう」と言い出したのですが、それは絶対ダメだと。巨大紙相撲は、等身大の力士を紙でつくって、本当の大相撲みたいにタニマチを募集して、お気に入りの力士を応援して、という過程で人と人とのつながりが生まれてくる仕掛けになっているのですが、「負けて悔しい!」という思いが次への原動力になるんです。平等に分配したらそこが崩れてしまうと思い、徹底的に戦いました。
井上: 任せるためには、どんな仕掛けが必要なんでしょうか?
土谷: 企画の段階で、必ず「ボケ」とか「バグ」を入れておくようにしています。計算されつくしたアートプロジェクトもあると思うのですが、そういう方たちのやり方を見ているうちに、逆に自分自身の持ち味は「曖昧さ」だと気づいたんです。
- ストラクチャーの強度をあげる
土谷: 企画を練る段階では、ストラクチャーの強度をあげることを徹底的に考え抜きます。ストラクチャーというのは、言葉だったり図だったり、色々な形で定着しないとしっくりこないのですが、ここがしっくりこないと失敗する。
井上: 「ストラクチャー」とはコンセプトみたいなものですか?
土谷: 例えば、長者町山車プロジェクトのストラクチャーは、「長者町の全てのプロジェクトを成功させたい」というものでした。そうすると、自ずと構造が決まってくるんですね。山車の製作現場は、町の中で一番大きな場所を押さえようとか、現代美術を分かりやすく説明するための山車づくりにしようとか、山車をつくることをアートプロジェクトに関わる筋トレにしよう、とか。
「どんどこ!巨大紙相撲」のストラクチャーは、「千秋楽をつくろう!」です。これが、「強い力士をつくろう!」だと、構造になっていかないんです。千秋楽だからこそ、幹になる。
井上: 「幹になる」という意味で言うと、ストラクチャーというのは中心となる柱のようなイメージなのかなと感じました。最初から見たい風景があって、それに対して枝葉末節を設計していくというよりも、大きな柱となる部分だけを押さえておけば、後の枝葉は勝手に育っていくというか。
土谷: そうですね。大工の棟梁が、材木の性質を見抜かないと大黒柱が建てられない、っていうのと近いのかもしれません。例えば、「一番太い木が凄いねじれてるな~」とかいうのを理解して、このねじれてるのをどうやって構造化していくか、という風に見抜かないとストラクチャーが立たないんですよね。
井上: やっぱり大黒柱に近いんですよね。大黒柱さえ立てば、あとはどんな屋根の形でもいい、というような。
土谷: そうですね。それでフォルムが決まってしまうぐらいの、プロジェクトの根幹となる部分であって、表層的なデザインの話ではないですね。
ストラクチャーの一つの側面として、「アクションにつながるような」という要素はあるかも知れませんが、どんなアクションになるかはイメージしていませんし、啓発的な要素も入っていません。ディレクティブではなく、あくまで成り行きです。そういう意味では、一番のほめ言葉は「お前馬鹿だね~」と言われることなんです。スキだらけっていうことですからね。スキや間があると誰でも入れる。
先ほど「任せる」という話をしましたが、頑固な部分は本当に幹のところだけで、あとは全て曖昧で、たいていのことは許してしまいます。一度任せた部分は任せてしまいます。任せているのに、口出しはできないですし、知らないことは頑固になれないですから。(了)
関係づくりのヒントに満ちた土谷さんのインタビュー、いかがでしたか?長文お付き合い頂き有難うございました。
KOSUGE1-16のホームページはこちらです。